遺伝子侵略計画(脚本)
〇地球
〇研究所の中枢
メノーの長「抗争に敗北し、母星を棄て、どれほど時間が経っただろうか」
メノーの長「この船の動力もわずか。 いや、もう動力などというものはとうに尽きていた」
メノーの長「生き残ったメノーの民の生命と血潮を動力として、長い旅路を航行してきたのだったな」
乾いた笑いのようなものが暗い箱舟の中に響き渡る。
宇宙生命体、メノー823-452。
他の宇宙生命体に母星を侵略された彼らは滅亡の危機に瀕していた。
メノー823-452は雌雄が番いとなり、繁殖する宇宙生命体。
故に──全てのメノー823-452を殺さずとも、雌雄どちらかを殺し尽くせば自ずと滅亡するのだ。
特に彼らは雄に比べて雌が少なく、はるかにか弱い。
雄は屈強な戦闘民族であるメノーが他の宇宙生命体との戦いに敗北したのは雌を奪われたことに起因していた。
個体数を増やすことができなくなれば、継戦能力は失われる。
メノーの長「我々はこの星を探すために命を賭して航行してきたのだ」
メノーの長「我らが遺伝子に順応する可能性が最も高い生命体「ヒト」に巡り合うために」
メノーの長「さて、我々の中でも最も若く、繁殖適正が高い個体よ」
メノーの長「君にはこの青い星で繁殖をし、長い時間をかけて新たなる母星に作り替えてほしい」
メノーの若者「はい、長。それが私の使命であります」
メノーの若者「必ずや我らメノー823-452個体数を増やし、一族に繁栄をもたらして参ります」
メノーの長「ああ、期待しているぞ」
メノーの長「この星は目に見えない炎の膜で覆われている。 それを越えるための上陸ポッドはこの船には一機しかない」
メノーの長「この船の動力が完全に落ちる前にゆくのだ、メノーを背負う若人よ」
メノーの若者「御意」
部屋の隅で複数のコードに繋がれた箱。
これこそが彼をこの星に送り込むための箱舟だった。
若人は膝を抱えて窮屈な箱の中に座り込む。
その箱を閉じるのは──送り込む側の役割だ。
メノーの長「さあ、別れだ」
メノーの長「メノー823-452に栄光を」
〇黒背景
視界を覆う暗黒と共に、箱は青い星に落とされた。
メノーの間で残る言い伝えでは「海」とは万物の母と称されていた。
又は全ての生命が生まれる青い宇宙とも。
メノーは宇宙空間で息をすることは叶わない。彼らにとって宇宙とは常に死と隣り合わせの世界だった。
かくして、メノー825-423の最後の個体は青い星へ降り立った。
〇水中
この星での初めての感覚を覚えている。
若干の冷やかさが、全身を覆うような感覚。
そしてやや「しょっぱい」という味覚。
〇海辺
そして照りつける日差し。
それから波とよばれるものの音。
メノー「今も昔も、変わらない」
〇けもの道
「海」と呼ばれる場所で捕獲した魚なる生き物を小脇に抱え、メノーの若者は棲家へ戻る。
メノー「ん」
メノー「イヴ、出てきてはならないと言ったではないか」
イヴ「あ、メノーの声が聞こえました! どこに行ってしまったのかと不安だったのです・・・」
メノー「そうだったか、それは悪いことをしてしまった。一言声をかけるべきであったな」
メノー825-423の若人は、初めに降りた大地で偶然にも「ヒト」なる生命体の集落にたどり着くことができた。
いいや、集落とは言い難いものだった。
病か何かにより、それは既に集落としての機能を失っていたのだから。
かろうじて無事といえた「ヒト」の幼体を抱え、集落から遠く離れた場所に居を構えで10年余り。
保護した「ヒト」の幼体が雌であったことは幸運といえよう。
一方で事前の情報と比較し、この星に生息する「ヒト」は退化していた。
イヴ「あの、起きたらとってもお腹痛いですし、メノーの気配はないですし・・・」
メノー「ふむ、体の異常を感じたか」
イヴ「うん」
イヴは、いや彼女だけではなく。
『ヒト』は五感と呼ばれるものの半分を失っていた。
舌はあっても味覚はなく、目は存在するだけで視覚は機能していない。嗅覚は弱っており、完全に残されているのは触覚と聴覚のみ。
かつて生物ヒエラルキーの頂点にあった生き物は、これらの退化により底辺に落ち込んでいた。戦う術もなく病に弱い。
栄華を極め、自らの力で宇宙へ飛び立った種族の面影はそこにはない。
なんらかのきっかけで文明が滅び、個体数が激減した結果だろう。
唯一の救いは生殖能力が残されていることだろうか。ある意味奇跡かもしれない。
メノー「特に外傷は見えないが、食べ物に痛みがあったのだろうか。排泄の感覚はどうだ、水っぽくはないか」
イヴ「うんちは普通・・・」
メノー「そうか、であれば腹を下したわけではない。他に変わったことはないか」
イヴ「あの、朝起きたらお布団が湿ってて」
メノー「寝ている間に粗相をしたか、しかしこれでは腹痛との因果関係が────」
イヴ「ち、血の匂いがしたのです」
メノーと呼ばれる宇宙生命体の脳内に電流のようなものが走った。この星に降り立つまでの船で得た知識にフルで検索をかける。
その結論は。
メノー「今日は少しだけ豪華な食事を作るとしよう。 たとえば、お祝い事のような」
イヴ「今日はお誕生日じゃないですよ!?」
メノー「それでもこれは、めでたいことなのだ」
イヴ「お、おねしょしたのにですか・・・」
〇廃列車
はるか昔に人工的に作られた洞窟に2人は住んでいた。かつては「ヒト」を運ぶ役割があった鉄の塊ももう動きはしない。
メノー(寝たか)
すう、すうと寝息を立てるイヴの髪を撫で、メノー825-423は土臭い天井を眺めた。
メノー「私は君を繁殖のための胎としてしか見ていないのに、なぜそんなにも無警戒なのだ」
メノー「特に君の体は子を成す準備が出来た、と合図したばかりなのだぞ」
ということを説明したものの、イヴには理解できていないようだった。
メノー「はぁ──そう育ててしまった私にも一端の責はあるか」
メノーの背から1本の触覚が伸びる。
イヴにも、同じメノー825-423にもほとんど見せたことのない手よりも長い器官。
甲殻のようなもので覆われたメノー825-423の体の中でも唯一無二の異質なそれは、同種の雌にふれるための触手であった。
つまりはメノー825-423の遺伝子を目の前の少女に流し込み、この星の生命を媒介にして同種を増やすための兵器。
ゆらゆらと、ゆらゆらと。
イヴに触れるか触れないかと戸惑うような動きをしてから──メノーの背へ戻っていった。
メノー(まだその時ではない。 イヴにはこれは大きすぎるではないか)
メノー(せっかくの母体候補だ、壊してしまうのは避けねばならない)
メノー(しかして──できるのならば同種の雄のモノを受け入れたかっただろうに)
〇睡蓮の花園
イヴ「ええと、鼻をつつくような匂いと、ザラザラの葉っぱ? うう、わかりません・・・」
メノー(昔は匂いの判別がついたのだが、成長するにつれて嗅覚が衰えてきたな)
メノー「イヴ、無理しなくてもいい。 薬草は私が見つけた分で足りているのだから」
イヴ「でもイヴはメノーの役に立ちたいです」
メノー「そうか。ではそこで水遊びをしているとよい」
イヴ「手伝いになっていません・・・」
メノー「私は君が手の届く範囲に居てくれたらそれで良いのだ」
イヴ「そ、そうなんだ・・・」
メノー825-423の寿命は長く、生まれてから100年ほどで大人となり120年で成長を止める。
一方でこの星の「ヒト」の成長はメノーに比べて早く、30年ほどで天寿を全うするらしかった。
100年の寿命を持つと聞いてはいたが、30年までに縮まっているとは予想外だった。
メノー(存外、時間がないのかもしれん。 生殖可能な期間が何年間なのかも見通しが立たない)
イヴ「め、メノー! 助けっ・・・足が・・・!」
メノー「どうしたイヴ!!!」
声のした方向へ視線を流す。
- このエピソードを読むには
会員登録/ログインが必要です! - 会員登録する(無料)

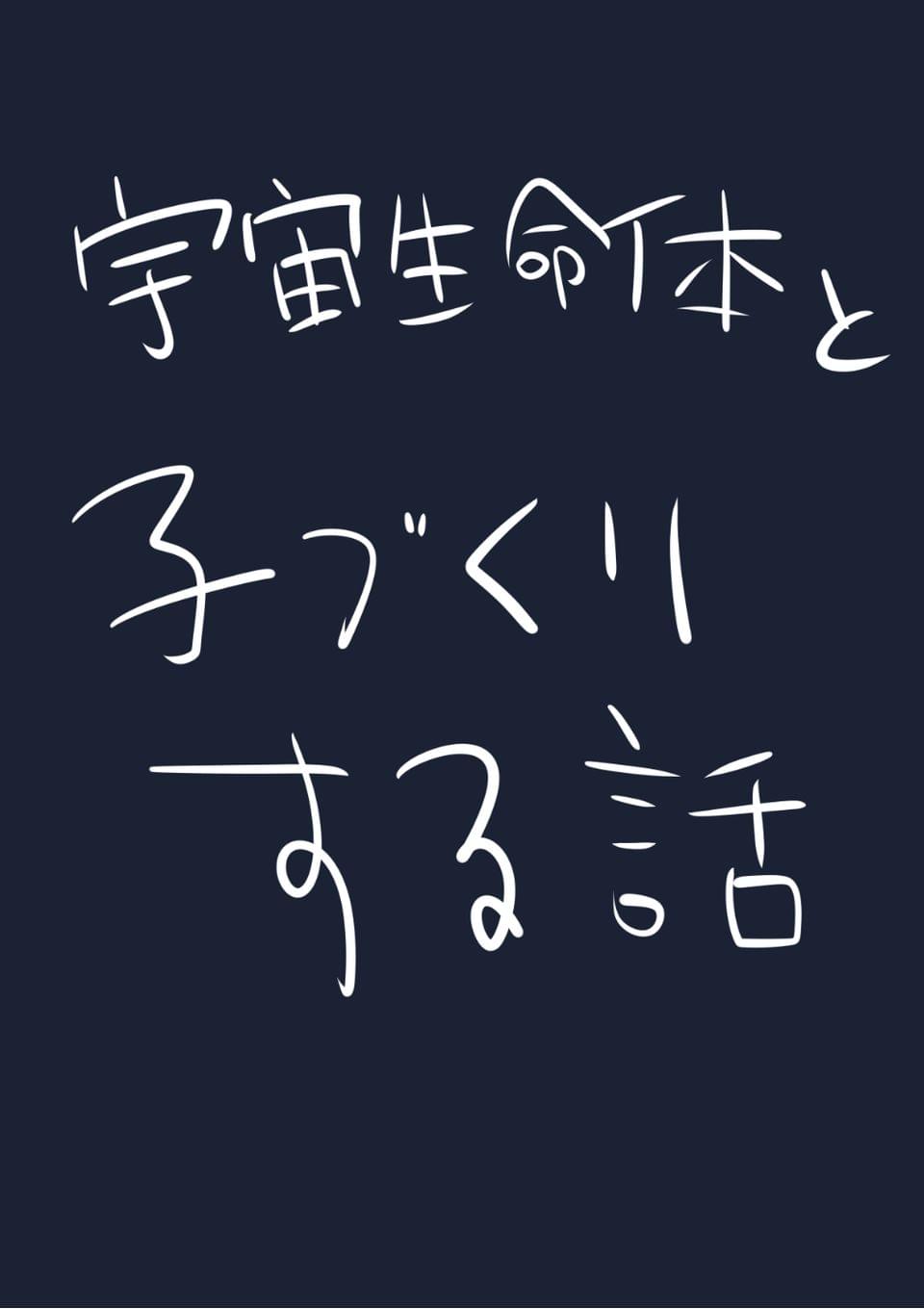


地球外生物は地球を侵略するだけかと思ったら、この物語では新たなアダムとして遺伝子を運んできてくれた救世主の側面もあるところが斬新でした。イヴから人間の姿そのままのカインとアベルが誕生したから、ここからまた人類の新たな歴史が始まるかも。それにしても、赤飯でお祝いする習慣をメノーが知っていたのには茶を吹いた。