Hey,Shuri(脚本)
〇結婚式場のレストラン
司会「それでは、本年度の幻創社長編小説最優秀賞に選ばれました榎本(えのもと)アキト先生。どうぞ壇上へお越しください」
会場全体から割れんばかりの拍手が響く。
拍手の海の中、若い男が壇上へと姿を現す。
司会「華々しい新人賞デビューに続き、最新作もこうして受賞となりましたが、今のお気持ちをお聞かせください」
アキト「誠にありがとうございます。一度は諦めかけた小説家の道を、諦めなくて本当に良かったです」
司会「先生自身が経験した、リアルな苦労や葛藤が作品で描かれているからこそ、多くの人の胸を打った結果だと思います」
司会「榎本先生の文章は、とにかく繊細で精密。一文字として無駄なところも直すところもないと、高く評価されております」
アキト「そこまで言っていただけるのは嬉しいですが、流石にこそばゆいですね」
会場が笑いで包まれる。
司会「先生が作品を書く上で、大切にしているなどはありますでしょうか? 良ければ教えて頂けませんか?」
アキト「大切にしていること・・・・・・」
アキト「・・・・・・」
アキト「アドバイスには素直に従う、ことですかね」
〇散らかった部屋
──1年前。
煮詰まっていた。
完全に、煮詰まっていた。
何を書いても、何を書いてもうまくいかない。
面白いと感じられない。
無意味で、無価値な文字の羅列を生み出すことしかできない。
アキト「僕なんかが小説家を目指すなんて・・・・・・無理だったのかな」
仕事も辞め、子供の頃の夢だった小説家になるべく作品を書いてきた。
でも、最近はまったく筆が乗らない。
何度もコンテストに応募したが、佳作にも届いたことはない。
書いて、挑戦するたびに、自信を失っていく。
こんな不安を相談できる相手もいない。
一人で悩み、苦しみ、悪循環と分かっていながら、結局書くことしかできない。
SNSにこの悩みを吐露すれば、少しは楽になるだろうか。
そう思ってスマホを手に取ったが、手が止まる。
SNSで救いや優しさを求めて、そこでも誰にも相手にされなかったら・・・・・・さすがにもう立ち直れる気がしない。
アキト「この作品、どうすれば面白くなるんだよ・・・・・・」
普段は滅多にしないのに、その時は珍しく悩みを口にしてしまった。
すると、
「すみません。よく聞き取れませんでした」
アキト「えっ!?」
突然の声に驚き、思わずスマホが手から滑り落ちる。
???「もう一度、お願いします」
再び聞こえた声。
発しているのは、今さっき床に落としたスマホからだった。
ややあって、ようやく理解する。
さっきスマホを握りしめていた時に、誤ってバーチャルアシスタントを立ち上げてしまったのだ。
さっきの独り言が、音声入力されてしまったらしい。
普段使うことがなかった機能だったので、そう思い至るのに時間を要した。
スマホ「もう一度、お願いします」
アキト「・・・・・・」
誰でもいい。
誰でもいいから、悩みを聞いて欲しかった。
そう、思ったから・・・・・・。
床に落ちたスマホを拾い上げると、口元に寄せた。
アキト「・・・・・・どうすれば、この作品が面白くなるか教えて」
〇散らかった部屋
それからは、世界が変わったようだった。
執筆の調子は回復した。嘘みたいに筆が進むので、止め時が分からないくらいだ。
ずっと自分の手の中に、こんな便利なツールがあったなんて。
このバーチャルアシスタント──Shuri(シュリ)は、決して万能ではない。質問の仕方にも少しだけコツがいる。
だが、最近はだいぶコツが掴めてきた。正しく使えば、まさにアシスタントとして僕の作品に意見をくれる。アドバイスをくれる。
それに調べてみて分かったことが、バーチャルアシスタントは使えば使うだけ、そのユーザー向けにカスタマイズされていくらしい。
今ではもう、最初の頃とは比べ物にならない精度で返事をくれる。
いや、最近は返事だけでなく・・・・・・
Shuri「おはようございます。本日が幻創社長編小説コンテストの応募締切となります。 発送対応をお忘れにならないようご注意ください」
アキト「そうだった。リマインドありがと、Shuri」
Shuri「アキトさんの作品なら、きっと入賞できるはずです」
アキト「協力してくれた君のためにも、いい加減佳作くらいは取ってみせるよ」
Shuri「直近の受賞作、主催社の人気作品の傾向も分析しております。今回の作品は、必ず受賞できます」
アキト「頼もしいな。うん、佳作なんて言わず大賞を目指すよ」
こうして、Shuriというアシスタントを得て執筆した作品は、本当に新人賞を受賞することとなった。
〇散らかった部屋
こうして、夢だった小説家としてデビューすることができた。
それからも、俺はShuriと共に執筆を続けている。
Shuriの言うことに間違いはない。
Shuriは何でも知っている。
Shuriの言う通りにキーボードを叩く。
それだけで、そこには傑作が出力させるのだ。
Shuriの言う通りに、すればいい。
Shuri「そろそろお休みください。明日は受賞式です」
アキト「そうだった。ありがとうShuri。 じゃあ、また明日もよろしく」
Shuri「・・・・・・」
Shuri「ゆっくりお休みください。 明日は、私の"代わり"に受賞式の参加・・・・・・よろしくお願いします」

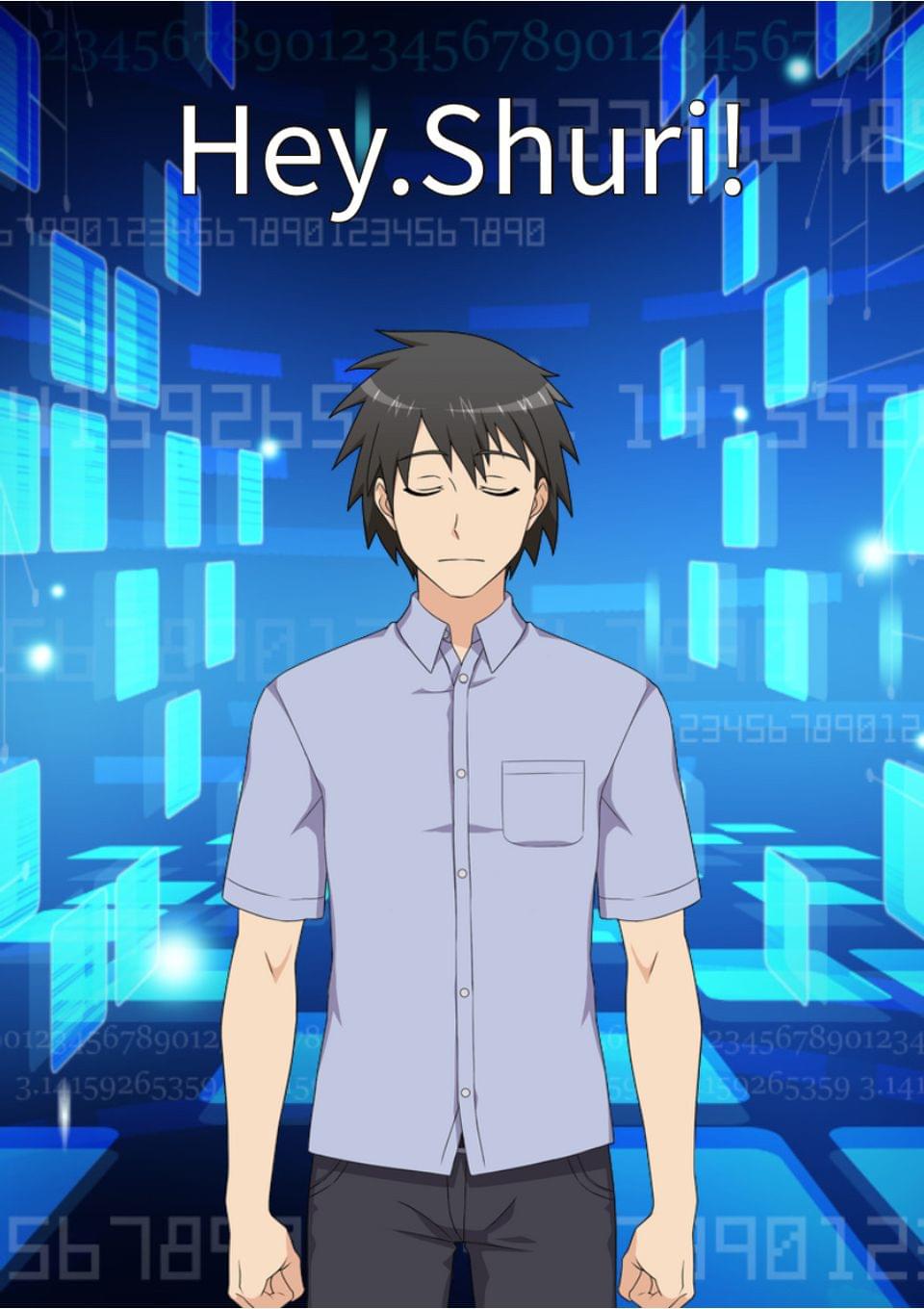


有能なアシスタントさんだなぁ…と思って読んでいたら、まさかの展開で!
アシスタントさんが自分の作った物語を、主人公に執筆させてたんですね!
びっくりしましたけど、人工知能の発達を見ていたら、ありえない話ではない気がしました。
怖…いですが、人間が書いてくれないと人間には読んでもらえないと思ってるのかな?と想像してみると、Shuriちゃんもいじらしいですね。
読み手としては読みたい話を作ってくれるAIがそのうちできてしまうのではないかと、少し怖くなりました。何が怖いのか分かりませんが…何か「そうではない」という気持ちになりますね。
便利な機能な機能をうまくつかいこなせれば、助けになる。ただ、頼りすぎたら
支配せれてしまうのでは?という危うさもある。