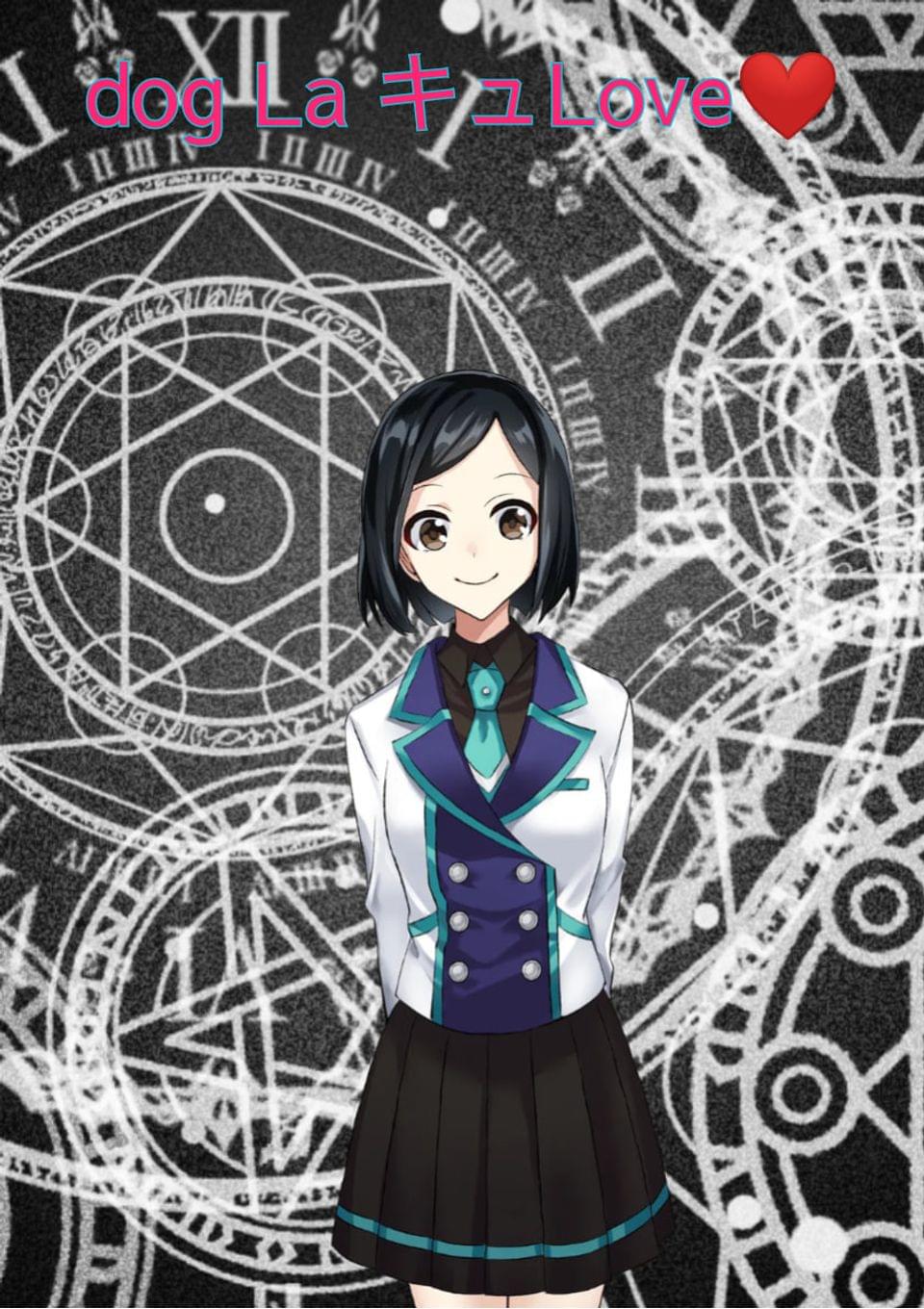第4話 恋のライバル現る?(脚本)
〇ゆるやかな坂道
最近、ミサトと散歩していると、時々会う奴がいる。
タカシ「また会ったね。カッコイイ犬だね。名前はなんていうの?」
みさと「シロです。」
タカシ「で、君の名は?」
みさと「え、私ですか? えっとー」
ドッグラLaQLove「こんな奴に教える必要なんかないぞ!!(ワンワン)」
みさと「こら、シロ吠えないで。えっと、ミサトです。」
タカシ「ミサトちゃんか、ヨロシクね。」
ドッグラLaQLove「早くどっかに行っちまえ(ワンワン)」
みさと「こら、シロ!! 人に向かって吠えたりしたらダメでしょ!」
え、、、ミサトに叱られた──
次の日からミサトは洋服をあれこれ迷うようになったし、急に髪型も気にし始めた。
みさと「さ、シロ散歩に行こ──」
これまでは毎回コースを変えてたのに、最近はいつも同じ道。もうこの道は飽きたよ──
タカシ「やあ、また会ったね」
みさと「こ、こんにちは。」
またお前か!! なんでしょっちゅう会うんだよ・・・!?
タカシ「ミサトちゃんはこの近くに住んでるの?」
みさと「は、はい・・・」
タカシ「そうか、実はボクもなんだよ。だからよく会うんだね。」
みさと「そうなんですね──」
ドッグラLaQLove「おい、お前、なんなんだよ。俺のミサトに近づくなってば!!!!」
〇総合病院
数日後、俺はミサトと病院にやって来た。退院後に1回だけ医者に診てもらわないとならないそうだ。
タカシ「やあ、ミサトちゃん」
みさと「あれ? なんでこんな所に?」
タカシ「僕はこの病院のドクターなんだよ。」
みさと「え──、そ──なんですか──」
クソ、ミサトの奴、なんだよデレデレしちゃって。俺のことは忘れてしまったのか?
ドッグラLaQLove「言いたかないけど、俺はミサトのために1度は命を捨てたんだぞ!!」
そんなことを言うと自分が惨めになるだけだ・・・
ドッグラLaQLove「あれ? ミサトは?」
〇病院の待合室
タカシ「僕は小児科のドクターなんだよ。」
みさと「そーなんですねー。」
タカシ「診察が終わったら、地下の食堂でパフェをご馳走してあげるよ」
みさと「やったー」
〇学食
俺を放ったらかしにして、ミサトはあのイケメンとタラタラとお茶してたらしい
ドッグラLaQLove「そんなこと許せない。もう俺は怒ったぞ。俺を怒らせたらどーなるか思い知らせてやる」
〇病院の廊下
その日の夜、俺はこっそり病院に忍び込んだ。もちろん奴に会うために・・・
タカシ「ここは病院だぞ。犬は立ち入り禁止だ。さっさと外に出るんだ。」
ドッグラLaQLove「ちくしょう、エラそうに──。こうなりゃ仕方ない」
タカシ「うわ──、な、なんだお前は!!」
Dog la キュLove「我の名はdog La キュ Love❤神より聖なるパワーを与えられし者。真の勇者なり。」
タカシ「クソ、なんて力だ。人間の力じゃとても叶わない。」
Dog la キュLove「さぁ、泣きながら命乞いするがいい。そうすれば命だけは助けてやろう。」
Dog la キュLove「その代わり二度とミサトには近づくな!!」
タカシ「あ、キミはミサトちゃんの飼い犬じゃないか!」
Dog la キュLove「そうさ! ミサトに近づく奴は許さない。」
タカシ「待ってくれ。僕を殺すつもりなら、明日まで待ってくれ。」
タカシ「明日、5歳の女の子の手術をするんだ。僕がやらなきゃあの子は助からない。だからせめて明日までは待ってくれ」
Dog la キュLove「嘘を言うな。」
タカシ「嘘じゃない。調べてみればすぐにわかる。あの子は俺の手術を待ってるんだ。」
Dog la キュLove「お前、ミサトに惚れてるだろ?」
タカシ「あの子はまだ中学生だろ。僕の妹みたいな存在だ。それ以上でもそれ以下でもない。」
タカシ「第一、僕はもう結婚してるんだよ。」
Dog la キュLove「え!?」
俺は驚きのあまり、再び犬の姿に戻った。
タカシ「僕は妻を愛してるし、仕事に誇りを持ってる。ミサトちゃんは僕にとって可愛い妹みたいなもんだよ。」
タカシ「僕には少し年の離れた妹がいたんだ。でも妹は小さい頃病気で亡くなってしまった。だから僕は小児科のドクターになったんだ。」
タカシ「ひとりでも多くの子供を救ってあげたくて。」
ドッグラLaQLove「俺は奴の話を聞いて、急に自分が恥ずかしくなった。」
ドッグラLaQLove「ヤキモチ妬いてた自分が急にちっぽけな存在に思えてきたんだ。」
俺は1人で家に帰った。
〇一軒家
その夜、俺が1人でトボトボ家に帰ってくると
みさと「もー、どこに行ってたの? あちこち探したんだよ。」
ミサトに心配かけてしまった。ごめんミサト。
その時俺は急に目の前が真っ暗になるのを感じた。
みさと「シロ、どうしたの? シロ!!」
ドッグラLaQLove「ミサトの泣きそうな声が遠くで聞こえていた。」
俺は意識を失ってしまったんだ。