ホームメイド(脚本)
〇シックな玄関
扉を開けると、小綺麗な廊下が広がっていた。
彼「散らかってるけど気にしないで」
私「お邪魔します」
私は失礼がないように靴を揃えて家に上がった。
彼と付き合って半年、初めて家に呼んでくれた。
正直少し緊張している。
〇おしゃれなリビング
廊下の突き当りには広めのリビングがあった。
大学生の一人暮らしにしては広すぎるぐらいだ。
彼「父さんは一年中出張だから、ほぼ一人暮らしなんだ」
私「だったらもっと早く家に呼んでくれればいいのに」
彼「ごめんね。なかなか家が片付かなくて」
彼「その代わり今日はごちそうするからさ」
私「やったー!」
彼「じゃあ、早速料理作っちゃうね」
私「わたしもなにか手伝ったほうがいい?」
彼「大丈夫、ここでゆっくりしててよ」
私「はーい」
そう言うと彼はキッチンのある部屋へ向かった。
〇黒
何でも率先してやってくれる彼は、私の自慢だ。
〇大学
彼は私が化粧をしていると、とても悲しそうな顔をする。
どうしてって聞くと。
彼「そのままの君が素敵なのに」
だって。
今までそんなふうに言われたことはなかった。
それ以来、流石にメイクをしないわけには行かないので
ナチュラルメイクを心がけている。
でもそれだけじゃない。
毎日、私の分のお弁当まで作ってくれるのだ。
しかも、野菜を中心としたヘルシーなやつを。
野菜中心でも食べごたえがあり、とても美味しかった。
どうやって作っているのか聞くと
彼「愛情かな」
なんて真面目な顔をして答える。
私は彼のそんなところも好きだった。
〇おしゃれなリビング
そんなことを一人で考えていると、キッチンの方からバタバタと彼が駆けてきた。
彼「ごめーん。バター買い忘れちゃったから、ちょっと家出るね」
私「わかったー」
彼「恥ずかしいから、あんまり家の中見ないでね」
そう言うと、彼は部屋から出ていった。
彼が出ていったのを確認すると、私は行動に移った。
前々から彼の家に来たら知りたいことがあったのだ。
それは、あの料理の美味しさの秘密だ。
彼は毎回私の料理を作ってくれる。
でも、私から何かを作ってあげたことはなかった。
もし家に行って作ってるところを見れば、レシピの一つでも見つけられたら私でも作れるかも。
今こそ秘密を探る絶好のチャンスだ。
〇おしゃれなキッチン(物無し)
私はキッチンへと向かった。
キッチンは整頓されていた。
彼の性格が如実に現れている。
変わったところはなかった。
奥にある業務用の冷蔵庫以外は。
レストランの厨房にあるでかいアレだ。
私(この中にまさか秘密が?)
私は冷蔵庫の中を開けた。
〇おしゃれなキッチン(物無し)
開けた瞬間、冷気が私の体を包んだ。
しかし、それは冷蔵庫のせいではなかった。
中にあったのは・・・。
私は大きく息を吸った。
叫ぶためだ。
しかし、私は叫ぶことはなかった。
叫ぶ前に、私の後頭部に衝撃が走った。
〇黒
私の意識はゆっくりと暗闇へと落ちていった。
〇黒
──────。
人間は食べなければ生きていけない。
生きている限りは
常に食べ続けることになる。
つまり
より良いものを食べようと思うのは
人間の欲求として正常だ。
〇おしゃれなリビング
母さんは僕が小さな頃に家を出ていった。
それからは父さんと二人暮らしだ。
といっても、父さんは出張ばかりで僕は家で一人ぼっちだった。
小さい頃から僕は一人で料理を作って食べていた。
〇おしゃれなキッチン(物無し)
自分で作ったものを美味しいと感じたことがなかった。
じゃあ、外食は美味しいかといえば美味しくなかった。
生きるためだけに美味しいと感じないものを食べ続けるのは苦痛だった。
僕は料理を人一倍研究した。食材の産地にもこだわった。
父さんは生活費をたくさん振り込んでくれたので困ったことはなかった。
でも、どんなに努力をしても僕は料理を美味しいとは感じなかった。
〇おしゃれなリビング
ある時、僕は家で豚を飼うことにした。
もちろん食べるためだ。
買っているうちに愛着も湧いた。
でも、僕はそのブタを〆て食べた。
食べているときは涙が止まらなかった。
そして同時に初めて感じた。
〇黒
美味しい、と。
美味しさが溢れ出した。
噛みしめれば噛みしめるほど
飼っていた記憶を思い出せば出すほど。
僕は一つの真理に達したのだ。
料理を美味しくするのは『愛情』だと。
〇おしゃれなリビング
僕はしばらく動物を飼い、食べるということを繰り返した。
美味しかった。
しかし、美味しさというものも飽きが来るのを初めて知った。
僕は再び飢えた。
美味しいものを食べる喜びを知ってしまったから。
より愛するものを食べたい。
そう思うのは自然なことだった。
〇おしゃれなキッチン(物無し)
僕は目の前にある肉の塊を食べる分だけ切る。
この肉はステーキにしよう。
熱したスキレットに肉を乗せると
香ばしい匂いがあたりに漂った。
焼き過ぎは良くない。
折角の柔らかい肉が固くなってしまう。
僕はステーキをレアに仕上げると、食卓へ運んだ。
〇おしゃれなリビング
その部屋にもう彼女はいない。
本当はこのステーキも食べてほしかった。
美味しいって言ってほしかった。
でも、彼女はもうこの部屋にいない。
・・・大丈夫。
彼女は僕の心のなかで生き続けてくれるのだから。
僕はステーキに向かって手を合わせる。
このステーキはきっと
今まで食べた何よりも
美味しいに違いない。
彼「いただきます」

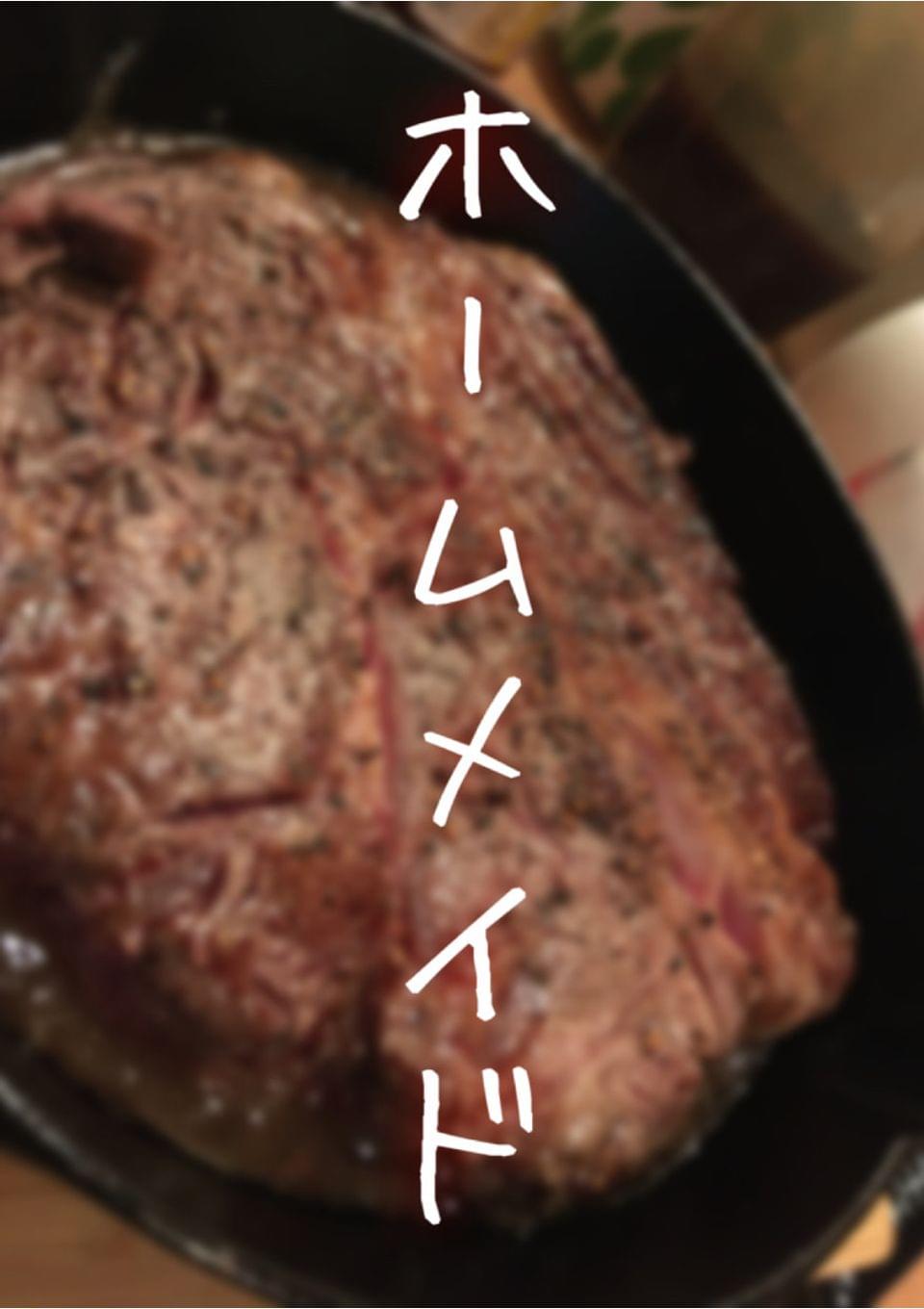


「料理は愛情」という言葉は、日本中どこでも言われていたりしますが、まさかの「愛情」でしたね……。じわじわと伝わる狂気に寒気がします。
料理をおいしくする愛情っていうのは間違ってませんが、彼の方向は間違ったところにいってしまったようですね。
冷蔵庫の中身って…やっぱりアレですよね。
ものすごい展開にびっくりしました。小さい頃からほぼ独りで暮らしてきて、愛情に飢えていた故なんでしょうか…。同感はできないものの、ぞっとしたのと同時に彼の歪んだ愛情と寂しさが伝わってきて切なくなりました。